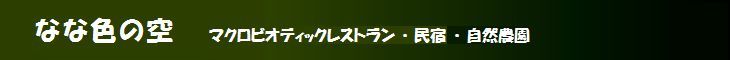自然農園 in なな色の空
なな色の空の農園の基本方針は「自然を収奪せずに、自然に沿う農業をする」ということです。
ここで言う、自然とは「自然の森」をモデルにしています。
自然の森は耕さなくても常に土が柔らかく、肥料をやらなくても肥沃さを保ち、農薬を使わなくても虫や病気の問題がなく、植物の光合成による炭水化物の生産性は農地の2倍ほどあります。
自然農業とは自然の森がどのようにして、土を守り、肥沃にし、生態系のバランスを保ち、虫や病気の害を防ぎ、太陽、雨という自然のエネルギー、資源を最大限に利用できるのかということを、学び、農業の具体的な技術として応用する農業です。
なな色の空の農園の基本姿勢は以下の4つです。
1. 完全無農薬、無化学肥料
自然の生態系を乱して、人間の健康を害する農薬や化学肥料を一切使いません。
農産物は食べ物です。食べ物に「虫や病気を避けるため」とか「商品価値を高めるため」といって、
「毒物」を使うことは、すべきではないと考えています。
自然は循環しています。投入された毒物は多くの生物を害し、最後に人間自身に帰ってきます。
2. 多様性
自然の森には、病虫害の元になる虫も微生物も住んでいますが、大発生して、病虫害を発生させることは決してありません。それは、多様な植物、動物、微生物によって生態系のバランスが保たれているからです。
しかし、農地では人間が食べる作物や、お金になる作物だけを一度に沢山作るため、単一性になりがちです。この単一性が生態系のバランスを崩し病虫害発生をまねく主な原因です。
農園ではなるべく多くの種類の野菜、穀物、豆、ハーブなどを植え、輪作をし、また、果樹などの木々をうえ、多様性を富ませ、病虫害と呼ばれる虫や微生物が共存しつつも大発生しない健全な農園の生態系バランスを保つことを目指しています。
3. 不耕起・草生栽培
生きている豊かな土を保つためには、土の表面を自然の森のように植物や枯れ草などで覆い、土の表面を太陽や雨に直接さらさないことが肝要です。それは、土の中で最も栄養が豊かであり、微生物の活動が活発な「表土」まもり、流出を防ぐという意味を持っています。
そのために基本的に不耕起・草生栽培をしています。やむを得ず耕すことになった場合、草マルチなどで、表土を太陽や雨にさらさないことを心がけています。
4. 循環(有機物の還元)
自然の森では誰も肥料を入れたり、耕したりしませんが、土は年を経るごとに豊かになってゆきます。それは、太陽の光を光合成によって取り込んだ植物の生産物が、全て、土に返り、循環しているからです。
しかし、農地では田畑から農作物を収穫しますので、結果的に「収奪」がおこってしまい、自然の森のような完全な循環をすることができません。この「収奪」が、土壌劣化の主な原因です。
そのため有機物の循環を補うことが必要になってきます。農園では基本的に土を肥やすのは草であると考え、畑や土手や道に生える草を農地に還すことによって基本的な有機物の還元を行います。草だけでは足りない場合、米ぬか、油粕、堆肥などを必要に応じて補います。
----------------------------------------------------------------------
* ここに述べたは基本的な考え方を詳しく知りたい方は、Lessons From Nature をご覧ください。
なな色の空の住人紹介
村上 真平 (むらかみ しんぺい)
1959年、福島県田村市生れ。70年から有機農業を始めた農家の後継者であったが、82年、インドに渡りガンジー・アシュラムに一年間滞在したのをきっかけに海外協力の道に入る。85年からバングラデシュに6年間、96年からタイに5年間、民間海外協力団体(NGO)を通して自然農業の普及と持続可能な農村開発の活動に関わる。2002年、日本に帰国し、福島県飯館村に入植、「自然を収奪しない農の在り方と、第三世界の人々を搾取しない生活の在り方」を探求するために、自然農業、自給自足をベースにした生活をはじめる。
著書 - Lessons from Natrue(英語)
村上 日苗 (むらかみ かなえ)
1972年、静岡県浜松市生れ。92年から調理師、製菓衛生師として、ホテルレストラン、パン屋さん、洋菓子屋さん、イタリアンレストラン、自然食レストランで10年ほど働く。2001年より、農と食と生活のつながりの大切さを感じ、川口由一氏の提唱する自然農を学ぶために三重県にある赤目塾に2年ほど通う。
2003年に結婚し福島県飯舘村に住む。2006年4月より、マクロビオティック・レストラン「なな色の空」を始める。
|